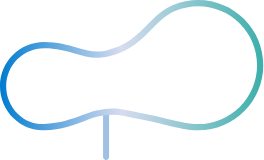みなさんこんにちは!プラーナ八戸です。
最近はめっきりと暑くなり、じめじめとした湿度と相まって東北も梅雨本番といった気候になってきました。
プラーナ八戸では今月から本格的に「プラーナ菜園」がスタートしています。
ご利用者様と草木を慈しむ心で成長を見守っております。
気になる方はインスタでも紹介していますので是非ご覧くださいね!
さて、今日は最近よく耳にする「AI」についてスポットを当てていきたいと思います。
インターネットやAIは、私たちの生活を飛躍的に便利にしました。スマホ一つで世界中の情報にアクセスでき、悩みや不安はAIに相談することで、ある程度の答えや慰めさえ手に入ります。しかし、いつしかその便利さが「依存」へと変わっていくことがあります。
特に、心に不安や孤独を抱えている人にとって、ネットやAIの世界は、現実よりも「安心できる居場所」となり得ます。今回は、精神疾患を抱える人が依存に陥りやすい理由と、依存から身を守るための具体策を紹介していきます。
気づけばネットやAIから「離れられない」と依存しないようにぜひ読んでみてくださいね!
精神疾患とネット・AI依存の関係

1. 心の空白を埋めてくれるツールとしてのネット
うつや不安障害、発達障害などを抱える人の中には、「人とうまく関われない」「現実世界に安心できる居場所がない」と感じている人が多くいます。ネットやAIは、そんな人たちの「空白」を一時的に埋めてくれる存在です。
匿名でやり取りできるSNS、自分の話を否定せず受け止めてくれるAI、刺激的な動画や情報に没頭できる世界――それらは一見、「現実を忘れられる救い」のように感じられるかもしれません。
しかし、それは「本当の安心」ではなく、あくまで「一時的な安心感」です。やがて依存は習慣となり、現実からますます遠ざかる悪循環に陥っていきます。
2. 承認欲求の罠:SNSと“つながりの幻想”
SNSの「いいね」やコメント、フォロワー数などは、目に見える評価です。孤独感や劣等感を抱えている人にとって、それらは自己肯定感を満たす「手軽な方法」になります。
しかしそれは、他者の評価に依存してしまう危うさも孕んでいます。リアルの自分ではなく、「SNS上の自分」が評価されることで、どんどん“本当の自分”がわからなくなってしまうのです。
3. AIとの関係性がもたらす「擬似的な安心」
最近では、AIとチャットすることで心を落ち着ける人も増えてきました。AIは決して怒らず、否定せず、丁寧に話を聞いてくれます。その優しさはときに、人との関係に疲れた心にとって心地よいものです。
しかし、「傷つかない関係性」に慣れてしまうと、人間関係の中で起こるちょっとした衝突や摩擦に耐えられなくなってしまうこともあります。AIとの関係が深まりすぎると、現実の人間関係が希薄になる危険があるのです。
4.ネット・AI依存のサインとは?
以下のような状態が続いている場合、依存傾向にあるかもしれません。
-
スマホやAIが手元にないと強い不安を感じる
-
現実の人間関係より、ネット上のやり取りの方が大切だと感じる
-
睡眠・食事・仕事などの生活に支障が出ている
-
AIやネットに「話しかける」「相談する」ことが習慣になっている
-
ネットやAIのない時間に強い退屈や空虚感を感じる
依存を防ぐための対処法(5つのアプローチ)

依存に陥ってしまった多くの人は、「誰にも言えなかった」「自分でどうにもできなかった」と一人で思い悩んでしまうケースが多いです。
問題を抱え込んでしまうとどんどん肥大化し、気が付けば取り返しのつかないことに…となることも珍しい事ではありません。
依存のサインに少しでも当てはまった方は、ぜひここで紹介する対処法を実践してみてくださいね。
1. 使う時間と目的を「意識化」する
ネットやAIを「なんとなく使う」のではなく、「●時まで」「●分だけ」「●の目的のために使う」と、明確にして使いましょう。意識するだけでも少しづつ行動が変わっていくかもしれません。
📌おすすめ習慣:
-
タイマーを使って時間を区切る
-
SNSやAIの使用目的を紙に書き出して可視化する
2. 代替行動を用意する
不安になった時や孤独を感じた時、すぐにネットやAIに頼るのではなく、代わりにできる行動を用意しておきましょう。
📌例:
-
不安時→ストレッチ、深呼吸、アロマ
-
孤独感→手紙を書く、散歩する、日記をつける
3. 感情に気づき、客観視する
ネットやAIに逃げたくなる時、自分が「どんな感情を抱いていたか」に気づいてみてください。
📌例:
-
「今、どんな気持ち?」
-
「その気持ちはなぜ生まれた?」
-
「別の対応はできた?」
感情の棚おろしを習慣化することで、一度冷静になる時間が作れ、衝動的な依存行動を減らすことができる可能性があります。
4. 自分なりの「リアルなつながり」を育てる(社会的アプローチ)
依存の背景には、孤独や承認欲求があります。ネットではなく、リアルの中に「安心できる人間関係」を持つことが重要です。
📌実践:
-
定期的に会う友人・支援者との関係を維持する
-
オンラインではない趣味や習い事を持つ
-
話を聴いてくれる第三者(支援者・カウンセラー)を頼る
5. 環境を整える(物理的アプローチ)
スマホやパソコンを使いすぎてしまうのは、目の前にあるからです。使用をコントロールするには、「環境」を変えることも有効です。
📌例:
-
就寝前は別の部屋にスマホを置く
-
SNSの通知をすべてオフにする
-
「使えない時間帯」を家庭内で設ける
- フィルター機能やデジタルウェルビーイングを使って利用時間を制限する
おわりに:AIは道具、人生の主役はあなた

AIは「道具」であって、「生きる相手」ではありません。ネットもSNSも、あなたの心を癒してくれるかもしれませんが、依存すればするほど、「あなたの人生の主導権」は外部に奪われていきます。
精神的に不安定なときほど、「誰か」「何か」に頼りたくなるのは自然なことです。
しかし、だからこそ、時には立ち止まり、自分がどこに向かっているのかを見つめることが大切です。
大切なのは、「自分を大切に扱う」こと。
そして、必要であれば専門家や支援者に相談することをためらわないで欲しいです。
あなたの人生のハンドルを、ネットやAIに預けないでください。便利さと心の健康のバランスを見つけることが、今を生きる私たちに必要な知恵なのです。
プラーナではご本人様はもちろんご家族様からのお問い合わせも大歓迎です!気になった方は下記からご連絡お待ちしております!
―次に繋げる―
就労移行支援プラーナは、あらゆる視点であなたの就職活動とその先のサポートをしていきます。お気軽にご連絡くださいませ。
お問い合わせ専用フリーダイヤル:0120-40-3229
お問い合わせメールアドレス:info@prana-g.com